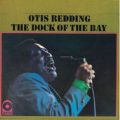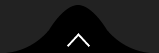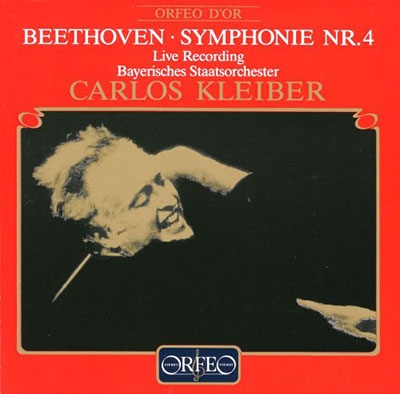
月曜日にポッドキャストの収録で、テーマの一つが「ベートーヴェンの交響曲」だったので、しばらくずっと聞いていました。
自発的にはあまりやらないことなので、折角ならと交響曲第1番から順に聴いていったり。
しかし、曲ごとにガラッと変わっていって、改めてすごいなと思いました。
ちなみに・・・
第一番 1800年
第二番 1802年
難聴が悪化して、「ハイリゲンシュタットの遺書」がかかれたのが1802年。
第三番 1804年
交響曲の1番、2番もとてもいい曲ですが、3番で激しく変化を感じます。
これって、なんだか、もう吹っ切れた!みたいな感じだったのでしょうね・・と収録時に話していたのですが、
本当にそのように感じられます。
ここから先は、収録ではうまくまとめてお話しできそうになかったこと。
まだ知らないことだらけで、思い違いもあるかもしれないけれど、ずっと聞いていて頭に思い浮かんだこと。
例えば、家族や恋人、家、財産、とても大切にしているものが失われたとき、人はどんな境地に陥るでしょうか。
世の中的には失恋が一番よくある「喪失」かもしれません、失われたときは海の底にいるみたいな、何もしたくない、光が見えない状態になる。
ベートーヴェンは、音楽家として軌道に乗ってきているときに最も重要な「聴覚」を失うかもしれないという状況に陥る。
それは恐怖、ストレス、喪失感、焦燥感・・などその手の言葉をどれだけ並べても足りないくらいのことだったではないでしょうか。
それを、そういう状態を克服するって、すごいことだと思います。しかもこの時代に。
今はいろんな情報で、克服した人の頑張っている姿や、言葉、過去の偉人の人生をなぞることができますが、(もちろんそれでも大切な何かを失うことは誰にとっても簡単ではないことは前提として)この時代そういうことがほとんど情報として入るわけではないとおもうので、ベートーヴェン自身の気持ちの持ち方で立ち上がったのだと思われますが、それでこの結果(音楽)ってすごい。
すごいのは、わかり切ったことでいまさら言うのもバカみたいですが、改めてすごいことだと思いました。
それで、音楽が素晴らしいのはもう聞けばわかるんですが、18世紀のこの時代に自分の手でつかみ取ったこの人生そのものが、なんというか啓蒙主義的というか、その象徴のような気がしてしまう。
うまく言えないのですが、ピアノ・ソナタや弦楽四重奏はおそらく家の中やサロンで楽しまれたりする個人的な面のあるものだけれど、交響曲はもう少し特殊で、演奏会で聴くものだから、もっとその時期その時期のベートーヴェンを取り巻くもの(社会、世間、年齢、実績、経験、技術)を全体的に捉えられる、それぞれの交響曲の躍動感は、この変わりゆく時代(客観)や、世の中における「個人」の捉え方(主観)とかその変動を聴くような・・段々何を言っているかわからなくなってきましたよ。
それで、どうして今この時代でもベートヴェンの音楽がこれほど聴かれるかって、膨大な情報社会において、情報を個人個人が選び取らなきゃいけなくて、うっかりすると知らないうちに情報の波に押し流されていることも考えられるわけで、それって、なんだか18世紀以前の市民と結果的に同じような感じ。情報が多すぎるのは、ないのと一緒みたいな。
だから強い思いで自分の足で立つためにベートーヴェンを聴く・・・わけではないと思いますが、無意識に脳に響くのはそうだったりして。
だって、なんだかとってもじっとしていられなくなるんですよ。ベートヴェンの交響曲は。
(竹田)
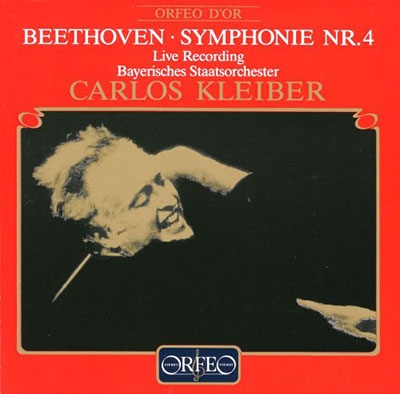
ちなみに、「ベートーヴェンの交響曲」というしばりで、最も好きなのはクライバー指揮のバイエルン国立管弦楽団演奏の4番です。