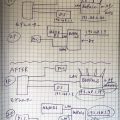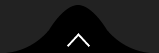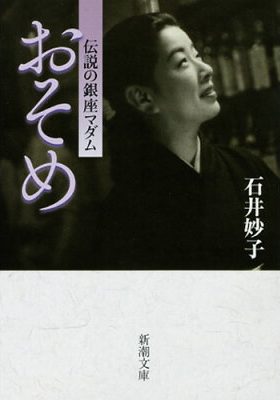
最近の積ん読3冊。
★ 音楽を考える 茂木健一郎/江村哲二
脳科学者の茂木健さんと工学部出身の作曲家の江村さんの対談。
「なるほどなぁ」とか「それはもっともだなぁ」などと思いながら読んでいて、「音楽はライブ!やっぱり生音じゃないと!」みたいな話のところで私の手は止まる。ちょっと頭に血が上る。クラシック音楽を中心に対談されるお二人に「いやいや、どんなオーディオ聴いてます!?」と独り言つ。
と思って本の発行年を見たら2007年5月1日。
2007年というのは、LINN KLIMAX DSが発売された年。しかも11月。世の中的に言えば「ハイレゾ元年」です。
じゃあ仕方ないか~。
今のオーディオお二人に聴いていただきたいな・・と思ってネットサーフィンすると、江村さんは47歳という若さで、発刊された年に亡くなられていました。
一方の茂木さんは、なんとSONYのハイレゾ推進のスペシャルコンテンツ2013年の記事で「ハイレゾはライブを超えた!」と言っている。
か、軽々しい・・・。
でも、この時点ではきっとそのように思えたのかもしれません。
それから12年。どれだけ、オーディオ愛好家と作り手が苦労したことか・・。
そして強調したいのは、ただただ「ハイレゾ」がライブを超えるのではえるのでは決してないし、ライブを超えるとか超えないとか、そういう問題じゃない。
確かにこの頃「原音再生」という言葉が各ブランドの広告によく使われていたし、2005年発刊の菅野沖彦先生の「レコード演奏家論」でもすでに、必ずしも生演奏が勝るわけではないと書かれたり、ライブとオーディオ、どっちがどうだ・・ということはよく話題にされていました。
でもはっきりと今は、オーディオとライブは別のものとして存在していて、しかも肩を並べていると言えるでしょう。
私がお店で「名曲深堀」イベントを打ちたい意味の一つでもあります。
今のオーディオだからここまで音楽を聴ける、真意に近づけるということ。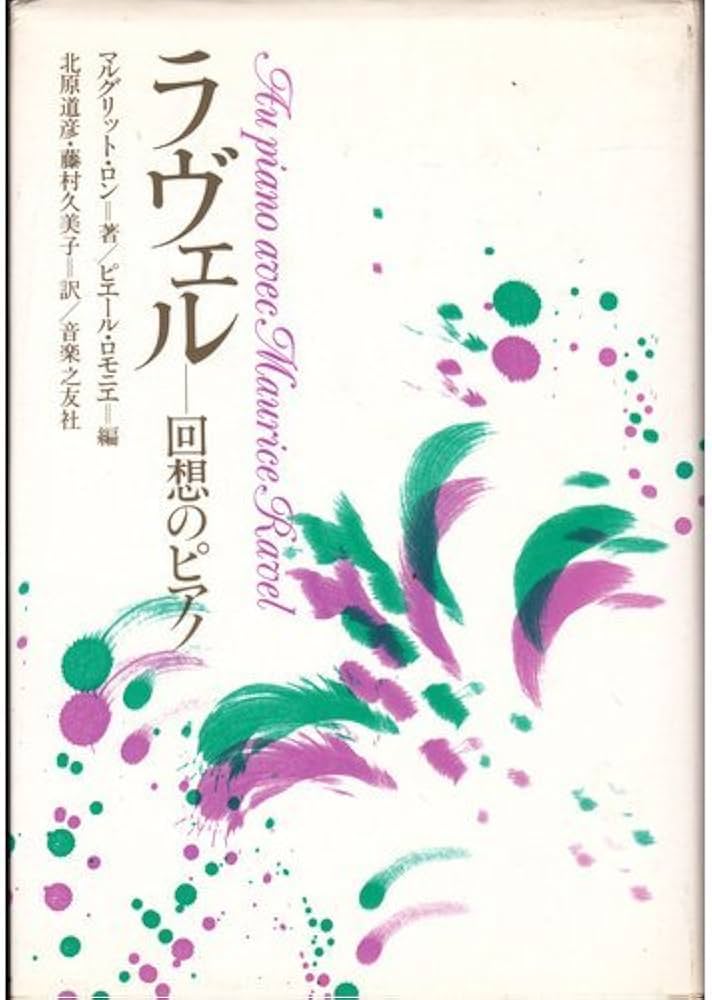
LINN 360EXAKT、茂木さんに聴いてほしいなー!
★ ラヴェルー回想のピアノ/マルグリット・ロン著/ピエール・ロモニエ編
次回のポッドキャストでラヴェルを取り上げるので、読んでいるのですが、今年生誕150年なのですよね。
著書のマルグリット・ロンは、ピアニストで教育者で、なんとなんと、
ラヴェルのあの美しい2楽章のピアノ協奏曲を献呈されたご本人である・・ということを読みながら知りました。
ラヴェルに付き添っての数々の演奏旅行でのエピソードからは、ラヴェルの人柄を知り、代表的なピアノ曲についての文学的とも思える解説。
まだ読み終わっていないけれど名著だなぁと思います。
そして、読みながら、ラヴェルの音楽にはやはりテンポやリズムが重要であることを感じさせらました。ボレロの演奏で指揮者のトスカニーニが速いテンポで演奏して、聴衆からは喝采を浴びたけれど、ラヴェルはカンカンだったそうな。晩年のトスカニーニとの和解に関してもロンの筆にありますが、ラヴェルの人柄を思わせます。
一言では例えにくいですが、センシティブさと大胆さを兼ね備えた、冷静と情熱の間のような人だったのではないかしら。
あと、とても面白かったのが、「ダフニスとクロエ」について書かれた表現が「ボレロ」のことと読めなくない部分もあり、2つの曲に共通点がないか探し聴きしてしまったり。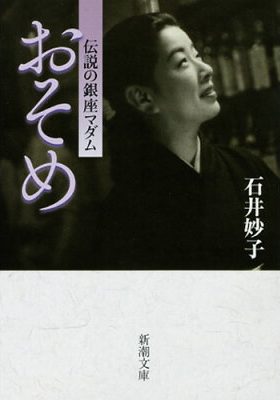
読みづらい文章もあるけれど、良い本。
★ 伝説の銀座マダム おそめ/石井妙子
映画「夜の蝶」は、京マチ子と山本富士子ダブル主演の銀座のバーの話。
川口松太郎の小説の映画化ですが、元々モデルがいて、銀座の夜を代表する「エスポワール」と京都から銀座進出した「おそめ」というバーのお話し。
その「おそめ」のマダム上羽秀さんについて書かれたものですが、これが当時の文化人の名前が次々に出てきてワクワクします。
「夜の蝶」も3度観ていますが、お話しの中のマダム、山本富士子をもってしても、ずっと奔放でずっと美しい人だったのではないかと思われます。
白洲正子や青山次郎、大佛次郎、いろんな人が上羽秀さんを語るのですが、秀さん自体は饒舌な人ではなかったか。ご本人が何と言ったかよりも、美しい人の残り香みたいな、そんな人。
気楽に読めてお勧め。
(竹田)