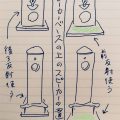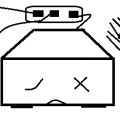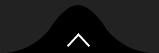本日ジャズ喫茶「ミュージックバード」のラジオの収録で午後から外出しておりました。
毎日同じことばかりいってスミマセン。
かける曲の選定をしている中で、面白いことがあって、今日はその話。
持っていった曲は、Jo Stafford「No Other Love」。
この曲を耳にしたのは、以前にもブログで触れたことがありますが、「Carol」というこの映画の中でのこと。

女性同士の恋愛の話・・といってしまえば、今はそうした映画も多く「LGBTね」と片付けられてしまいそうですが、ちょっとまってと言いたい。非常に情緒に満ちた映画で、昨年見た「君の名前で僕を呼んで」でも思ったのですが「人を愛する」ということにおいて、男女という枠の必要性を忘れさせるものがありました。
この劇中、印象的に流れるのがJo Staffordがしっとりと歌う「No Other LOVE」。
この歌はリリース当時の1950年、Billboardのヒットチャートの10位以内に入っていたよう。「空前の大ヒット」ではないかもしれませんが、それなりに売れたようです。
そもそも、ショパンの「別れの曲」で知られるエチュードNo.3に歌詞を載せたもの。
ですからメロディには耳馴染みがあります。Wikipediaを覗くと、ショパン本人が、こんなに美しい旋律は二度と見つけられないだろうと言ったというエピソードが載っています。(どこに書かれているのか探してみたいですね)抑制をきかせた中に一時感情の発露があって、また収束していく・・というような雰囲気は、曲自体が持っているものですが、Jo Staffordもそのように歌い上げます。タイトルの「No OTher Love」だって・・他にない、つまり唯一の、人生で一度の、本当の…。意訳すれば、これこそが愛・・というようなことで、歌詞はそれを証明するような内容。それ以上のことはないほどに、このタイトルに全てが集約されています。
そんな歌が、1950年代の女性同士の恋愛を描いた映画の中で、とても印象的に使われます。
この映画の舞台はアメリカですが、別の映画、第二次世界大戦前後の英国が舞台の「イミテーション・ゲーム」にも少し触れたい。コンピューターの基礎を築いたとされる英国の数学者アラン・チューリングについて描かれた映画で、偉業を成し遂げたチューリングですが、1952年に同性愛の罪で逮捕されます。彼の死後50年以上も経てから、その罪は恩赦になりますが、とにかく1950年代というのは世の中的に、そういう時代だったのですね。
話があちこち行きます。
この「Carol」という映画には元になった小説があって、それは実は、パトリシア・ハイスミスが1952年に書いた私小説なのだそうです。パトリシア・ハイスミスといってピンとこなくてもアラン・ドロン主演の映画「太陽がいっぱい」の原作の作者といえば、わかる方も多いはず。
しかも、彼女はクレア・モーガンと言う別名義で出版していたため、彼女の作品だと言うことはつい最近になってわかったのだとか。
また別の側面。「No Other Love」に歌詞をつけたのは誰なのかなと思って調べたら、Bob RussellとPaul Westonという二人の名前が必ず出てきます。
どっちがどういう役割とは書かれておらず、曲自体はショパンのものだし、Bob Russellは歌詞を作る人のようなので、編曲がPaul Westonなのかなーと予想しているのですが、いまいち明確な表記がない。
で、ネットサーフィンしていたら、Paul Westonは1952年にJo Staffordと結婚し、その後の生涯を共にしているのですね。「No Other Love」がリリースされた1950年に、彼はStaffordと一緒にコロンビア・レコードに移籍したようですし、この2年後に結婚しているとなると、この歌が歌われた時二人は絶賛大恋愛中だったということを想像します。
StaffordとWestonは、互いに添い遂げていますし、そういう点から見ると「No Other Love」は、生涯の伴侶(No Other Love)となる相手との恋愛中の幸せな歌(とはいえある程度年を重ねてからの恋愛はそんな根明なものではないでしょうから、きっとこの歌のような感じなのでしょう)。
ですが、50年代前半のアメリカが舞台の「Carol」で使われるとなると、実らない恋愛の中での「忘れられない恋(No Other Love)」となるわけで・・・。
J-POPの槙原敬之が「もう恋なんてしないなんて言わないよ絶対」と歌うのは、「もう恋なんてできない(それくらい忘れがたい)」という気持ちの反転でしょう。
StaffordとWestonの「No other Love」、Carolの主人公の「No Other Love」。
この歌の二面性を見ると、映画劇中で使われることがとても皮肉な感じに思えてくるのです。
キャロルに登場する二人や、アラン・チューリング、それぞれの恋愛を、当時と今という時代に置き換えた時、その皮肉さは浮き彫りになってくる感じがします。
人はどうしても自由に生きることはできないのか、愛ってなにか、不自由なものか、ないほうがいいのか、その人の仕事も地位も名誉も関係なくなってしまうものなのか。などなど。
ところで、このネットサーフィン中に、とても面白い記事を見つけました。
映画評論家の町山智浩さんによるこの映画の解説なのですが、「淀川さんすげー!」と思う内容。Carolに興味がなくても、「太陽がいっぱい」をもう一度見直したくなる内容ですので、ぜひチェックを!!
町山智浩「Carol」
長くなりましたが、こんな内容、ラジオで流れるように説明できるはずもなく・・。
今日も反省の1日でした。それなのに、また10月に呼んでいただきました。
(竹田)